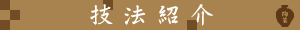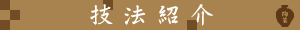|
[緑釉(織部釉)]
緑釉は日本で初めての人為的な着色釉です。大陸からの技術導入により、鮮やかな緑を発色させる銅を着色原料として使い始めます。緑・褐色・白の三色を使った中国の三彩(唐三彩)を真似た奈良三彩。これらの緑釉は鉛を媒溶原料として使用した800〜1000℃程度で溶ける低火度釉でした。
高火度の緑釉は17世紀頃、桃山後期に現れます。古田織部の美意識を反映して作られた多くの斬新なやきものの中で 木灰を媒溶原料とする緑釉は、茶碗から手鉢・向付等々
茶席で用いられる器に使われ、今では「織部釉」は緑釉の代名詞となっています。
またわずかに遡る桃山中期には、絵付技法の一種として 天然の硫酸銅(タンパン)を使った緑が黄瀬戸と呼ばれるやきものに見られます。
当倶楽部では、長石と木灰で調合した基礎釉に炭酸銅を8%加えた 1200℃以上で溶ける織部釉を使って、様々な緑の表現をしています。
晝間さんの皿は織部釉で全体を覆った総織部。掛ける釉の厚みを変えて緑の発色に変化をつけています。素地が軟らかいうちに施した力強い櫛目とともに「特別講師による講演と実技」(4/29)にて陶芸家
鈴木徹先生にご指導いただいたテクニックを存分に発揮しています。
流動して濃淡のできる織部釉は、金さんの小鉢にある線彫りや、小佐々さんの銘々皿のような荒目の石を押し付け表面に起伏をつけるなどの表現も効果的です。
織部様式は様々ありますが、風間さんの湯呑のようにスポイトを使って筋状に流し掛けた作品を 江戸時代の窯元の名前から、弥七田織部と呼んでいます。
野口さんの花瓶は紺を含む陶三彩に倣った配色です。素焼後にゴム樹脂(ラテックス)を部分的に塗って織部釉を施し、ラテックスを剥がした後に呉須や鉄釉などを筆置きした
大変手間をかけた作品です。釉薬が溶ける際、うまく混ざり合うよう 最後に木灰系の透明釉を全体に吹き付けました。
熊谷さんの長頸壺と井上さんの徳利・碗は、三彩の要素を取り入れつつより大胆な施釉・配色を試みています。
雨宮さんの湯呑と北岡さんの蓋物はタンパン溶液を筆置きした作品です。染み透るような緑は水溶性のタンパンならではの発色で、「抜けタンパン」といい、この緑は素地を通す性質を持っています。
筒井伸哉
|